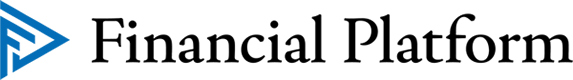企業型確定拠出年金(企業型DC/企業型401k)は、企業が従業員のために掛金を拠出し、従業員がその資金を自ら運用する年金制度です。税制優遇がある一方で、注意すべき点もあります。以下に、わかりやすくメリット・デメリットを整理します。
【加入者にとって】企業型確定拠出年金のメリット
- 税制優遇が大きい
企業型確定拠出年金最大のメリットは掛金が全額非課税(所得税・住民税がかからない)ことではないでしょうか。合法的に節税ができる仕組みです。
また、NISAと同様に運用益も非課税(通常の投資では約20%課税)な点も魅力です。所得税・住民税だけでなく、譲渡所得税も非課税となるためNISAよりも有利だと断言できます。
さらに、退職金として受け取る際も控除があり(退職所得控除または公的年金控除)、1粒で3度美味しい制度です。
- 老後資金の形成に役立つ
換金性がないというデメリットもありますが、原則60歳まで引き出せないため、確実に老後資金として積み立てることができます。財布にカギをかけることができるわけです。
また、積立資金を「自分で運用して準備する」意識が高まるため、お金に関するアンテナが鋭くなります。
- 掛金は企業が負担
通常、iDeCoでは加入者が自分で費用を負担しますが、企業の福利制度となるため全額企業が掛金を負担します。
最強の福利厚生といわれる理由です。
- 自分で運用先を選べる
投資商品は、投資信託、定期預金、保険など、運用商品を自分で選択できます。そのため、商品選定次第でリターンを高められる可能性がある
【加入者にとって】企業型確定拠出年金のデメリット
- 自己責任で運用する必要がある
運用成果はすべて加入者の責任となります。従来型の確定給付型企業年金や生命保険を活用した退職金制度と比べて、加入者の成果に対する負担が増します。元本割れのリスクがあるため、積立額よりも少ない金額しか受け取れないことがあります。ただ、定期預金のみ選択も可能だが利回りは低くなります。
- 60歳まで原則引き出せない
途中で解約・引き出しはできないため、急な資金需要には不向きです。換金性がないため、積立額は少なめにしておくようにしましょう。
- 投資知識が必要
運用先の選択や見直しには、一定の金融リテラシーが求められます。人によっては大きな成果が得られますが、金融リテラシーの低い人だとほぼ利益がない可能性もあります。商品選びを初期設定のまま放置すると、物価上昇以下の利益しか得られず物価上昇リスクを抱えることになります。
- 企業によって制度の内容が異なる
掛金額、マッチング拠出の有無、選べる運用商品の種類などは会社ごとに異なるため、導入企業により選択肢に大きく差が出ます。
退職時や転職時の投資資産の移管手続きが必要になり、移管先はiDeCo、次の勤務先の企業型確定拠出年金など複雑になります。
【導入企業にとって】企業型DCを導入するメリット
① 福利厚生の充実で人材確保・定着に効果
- 若手からベテランまで、老後資金形成を応援する制度として人気がある
- 「企業が従業員の将来を支援している」という姿勢を示せる採用時に強み
② 退職給付コストが予測可能
- 拠出額が毎月一定=確定給付型のような将来債務を抱えない
- 会計処理がシンプルで、企業財務の健全性維持に寄与
③ 全額損金処理でき、社会保険料も増えない
- 拠出した掛金は法人税の節税効果
- 給与とみなされないため、企業・従業員双方の社会保険料負担が増えない
- 導入方式によっては、企業・従業員の社会保険料を引き下げる効果もある。
④ 投資教育が金融リテラシー向上につながる
- 制度導入時に行う投資教育は、従業員の金融リテラシーの向上につながる
- 継続教育が企業文化として根付けば、社員の金融リテラシー向上→離職リスクの低下にもつながる可能性
【導入企業にとって】導入にあたってのデメリット・注意点】
① 初期導入と運営にコスト・手間がかかる
- 制度設計、規程整備、金融機関との契約、就業規則の改定など導入準備が煩雑
- 社員説明会や導入時の投資教育なども短期的には負担が大きい
- 支援会社の選定が難しい
② 投資教育の実施が「法的義務」
- 企業型DCは導入時・継続的な教育が法律で義務化(確定拠出年金法)
- 年1回以上の投資教育が必要で、実施体制(外部委託含む)の確保が求められる
- 投資教育の依頼先が少ない、金融機関だと当たり障りのない内容に終始しがち
③ 社員の投資知識で結果に差が出る
- 金融リテラシーの差が大きく、「定期預金一択で放置」というケースも
- 成果が社員の責任となるため、教育の質・頻度によって制度の効果が左右される
- 他責社員が多いと不満につながる可能性がある
④ 運用責任が従業員にあることで、不満の種になることも
- 元本割れなどで将来の受取額が期待より少ないと、会社に対する誤解や不満につながる恐れ
- 「福利厚生なのに損をした」と感じられないよう、中立的・実践的な教育が不可欠
| 視点 | メリット | デメリット |
| 福利厚生 | 採用力・定着力の強化 | 社内教育・制度理解に労力 |
| 会計 | 給付債務リスクなし、損金計上 | 長期的な掛金負担あり |
| 管理 | 拠出額が固定で管理しやすい | 初期導入コスト・手続きの煩雑さ |
| 社員対応 | 従業員に資産形成機会を提供 | 投資知識や説明責任が必要 |
導入はメリットも多いですが、「従業員への運用サポート」「制度運用の継続性」を意識した設計が鍵となります。ファイナンシャルプラットフォーム株式会社では、投資教育を有償で担当することができます。講師は国内有数の知識をもつ証券アナリストやCFP資格の保有者です。
【投資教育の重要性】を導入時の視点で整理
| 教育段階 | 内容 | 目的 |
| 導入時 | 制度概要/運用商品の特徴/リスクの理解 | 制度への信頼・理解を深める |
| 継続的 | 資産配分の見直し/市場動向/老後資金の試算 | 長期的な運用リテラシーの育成 |
| 退職・異動時 | 移管制度や受取方法 | 退職給付の自立的管理を支援 |
企業型DCを導入するかの判断ポイント
| 視点 | メリット | 注意点 |
| 福利厚生 | 採用・定着の強化に有効 | 金融リテラシーの個人差が影響 |
| 会計・税制 | 費用固定・損金処理可能 | 運用リスクは従業員負担 |
| 教育・管理 | 投資教育が組織的資産形成を支援 | 教育義務とその質の担保が必要 |
| 運用実務 | 金融機関や信託銀行との連携で整備可能 | 制度構築には外部支援が事実上不可欠 |
企業型DC導入ステップ(社内調整〜制度設計〜教育まで)
導入には数ヶ月の準備期間が必要です。以下に、導入までの流れをフェーズごとに整理しました。
▼【STEP①】導入検討・社内調整
- 目的整理(退職給付制度の整備、福利厚生強化 等)
- 対象者(正社員のみ/パート含むなど)と制度イメージの仮設計
- 経営層・労働組合・人事・経理部門との初期すり合わせ
▼【STEP②】制度設計・金融機関選定
- 拠出額の決定(全社員一律 or 等級別)
- マッチング拠出(社員からの任意上乗せ)の有無
- 加入年齢・勤続要件の設定
- 信託銀行(資産保管)、運営管理機関(SBI・野村など)の比較・選定
- 契約締結・規程類整備(就業規則の変更含む)
▼【STEP③】導入準備・社員説明会
- 対象社員向けに「制度説明会」を開催(多くは運営管理機関が実施)
- 投資教育の初回講義(動画・セミナー)
- 初期運用商品の選定支援(ライフステージ別・リスク別のアドバイスなど)
▼【STEP④】制度開始・継続教育
- 毎月の掛金拠出スタート(給与計算と連動)
- 年1回以上の継続投資教育を実施(法定義務)
- 運用商品の見直し案内、従業員からの問い合わせ対応(金融機関が代行することも)
導入が決定してから6か月。導入検討から1年程度の期間がかかると認識ください。ファイナンシャルプラットフォーム株式会社では、アイザワ証券のシステムを用いて、企業型確定拠出年金の導入とメンテナンスを行っています。
投資教育に力を入れて定着率を向上させたい場合。企業型確定拠出年金を採用時の差別化にしたい場合は、一度お問い合わせください。